研究の背景
私たちの体を貫く一本の「管」である消化管 gastrointestinal (GI) tract は、体内にありながら、その管の内側(管腔 lumen)は、生体にとっては体外であるといえます。そして、消化管の管腔という外部環境と、内臓や骨格、筋肉、神経組織などが存在する生体内とは、消化管を内張りする「粘膜 mucosa 」によって隔てられています。消化管粘膜では、食物として取り込まれた栄養分 nutrient を消化するために消化液を分泌したり、消化された栄養分を吸収したりするのみならず、管腔の状態を常時「監視」し、その情報を消化管壁の平滑筋に伝えて「蠕動反射 peristaltic reflex」を誘発したり、粘膜上皮細胞 epithelial cells に伝えて「分泌反射 secretory reflex 」を誘発したりします。このような腸管の機能によって、消化管内容物は消化管内を消化・吸収されながら適切に輸送されて行くのです。
消化管粘膜で感受された情報は、消化管壁内に存在する消化管壁内神経叢によって構成される「腸管神経系 enteric nervous system (ENS) 」によって処理され、腸管平滑筋や上皮細胞等に伝達されます。この腸管神経系は、交感・副交感神経系に加えて、第三の自律神経系と呼ぶべきものであって、消化管の基本的な生理機能を中枢神経系 central nervous system (CNS) からは独立して制御することが出来ます。腸管は、その生理機能を発揮するに当たって、極めて高い独立性、という他の臓器とは異なった特徴を有していますが、それは「消化管生理機能における中枢神経系」ともいえる、腸管神経系を壁内に有しているからなのです。このようなことから、腸管神経系を「第二の脳 second brain 」とか「小さな脳 small brain 」と呼ぶ場合もあるほどです。私たちは、このような腸管神経系を中心とした、消化管の制御システムの研究を行っています。(唐木)
● 実験機器
短絡電流測定装置
ヒト、ラット、モルモットの摘出腸管粘膜を使用して、経腸上皮膜起電性イオン輸送を、短絡電流として測定する電気生理学実験に使用します。
in vitro 腸管運動測定装置(マグヌス法)
摘出腸管の収縮弛緩を測定する装置です。
蛍光顕微鏡およびイメージングシステム
Zeissの倒立型蛍光顕微鏡とコンピューターに画像を取り込む装置です。研究室の暗室内に設置されています。
クリオスタット(凍結切片作製装置)
組織の薄切標本を作製するために使用します。
サーマルサイクラー(遺伝子増幅装置)
PCR装置です。RT-PCR法により、細胞や組織での遺伝子発現を検出するために使用しています。
吸光プレートリーダー
酵素抗体法(EIA)などで、組織やバス溶液、血液中の消化管ホルモン等、生理活性物質を測定するためなどに使用します。
● 研究室の日常・・・
09:00 朝は一杯のコーシーから始まる

コーヒー豆をミルに入れ、70 rpmでハンドルを廻すと、研究室内は香ばしい香りに包まれる。環境生理の朝だ。布製フィルター、ネルでコーヒーを淹れると、教室員はコーヒーカップを片手にその日の予定を話し合う。そしてそれぞれの研究に取り掛かるのである。

12:00 昼食
おなか空いた―― ボスの声が昼休みの合図。
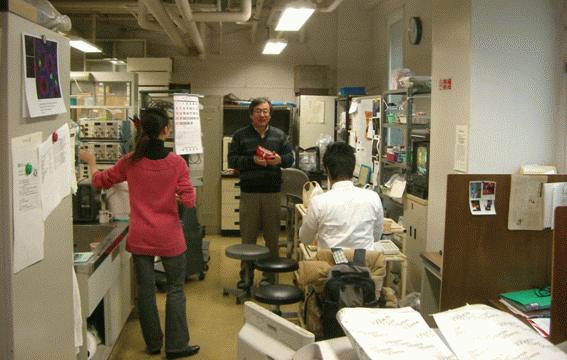
電気ポット、冷蔵庫、ホットプレート、ガスコンロ、炊飯器に鍋・フライパン類完全完備の当研究室では、料理も常の風景である。ニンニクやゴマ油の香りは廊下まで広がり、「さすが、消化管の研究室だ」と、研究所内に知らしめている。
時には何故か、ジャンクフードも食べたくなる。ペ・ヤン様を筆頭に、カップ麺は根強い人気を保っている。実験データを整理し、ちょっと良いグラフが描けた日には、ヤン様に湯を注いで待つ間にボスや先輩方の意見を伺うこともできる。
食後に欠かせないのは、NHK連続テレビ小説と、やはりコーシーである。

そして1時、
ごちそうさま―― 再びボスの声と共に、メンバーはそれぞれの作業に帰ってゆく。
18:00 夕食??

実験もします
実験は楽しく真剣に。
当研究室で行うメインの実験は生理実験だ。消化管を取り出し、切片にした平滑筋の運動を観察する装置と、粘膜のイオン輸送を観察する装置が、研究室の歴史と共に働いている。
繊細な組織を扱うのに欠かせないピンセットとマイクロ尖刀は、全員マイセットを持っている。実験に慣れたころ、自分専用の道具を授与されるのは嬉しいものだが、うっかりぶつけたり、硬いものをはさんだりすると容易に曲がるので、洗浄や保管にも気を遣う。
ほんの一瞬、などと思って誰かのピンセットを拝借し、迂闊にも先を歪めたりすると、「不器用」の称号を付けられ、半年間は酒の席でのネタにされてしまう。
生理実験の結果をバックアップするために、分子レベルの実験手法も取り入れている。受容体やペプチドホルモンを、特異的な抗体で染めだして観察する「免疫化学染色法」、同じく抗体を使ってタンパク質の発現量を調べる「ウエスタン・ブロッティング法」、また、遺伝子レベルの発現を調べる「RT-PCR法」など、手法は何でもありだ。
生理学の研究成果は、すぐには出ない。仮説を立てるのも、実証するのも、そう簡単にはいかない。こんな「ないないづくし」でも、真剣にそれを楽しみ、毎日ちょっとずつ実験結果を積み重ねていくのが、私たちの日常である。
